ロバート・ゴルディス著『神と人間の書』を読む1
- おいまつ÷のぞむ

- 2020年1月13日
- 読了時間: 2分
文脈に合わないような章句があると、それはよく、昔の読者によって加えられた大きな行間注や挿入と憶測された。正統派の読者が原本の中の異端的な感じのものと出会った時には、自分たちの見解と一致する、もっと紋切形のもので、その節のテキストを「修正」したり、補ったりすることをしたというのである。
この臆説は、一部の学者社会には一般的であるが、重大な疑いを免れない。質ねたいのは、なぜ異端的なテキストに、その反対者がわざわざ敬虔な想いを挿入する手間をかけるのかということである。そんな書物は完全に無視して忘れ去ってしまうか、昔のゲニザ〔倉庫〕に放り込んでしまえば簡単にすむことである。伝道の書は因襲的な注釈者の手で書き直された異端的なテキストであったという仮説がひところ流布していた。この書物の内容および文体に対するさらに深い洞察が、その内的単一性と統合性とを明らかにしたので、この仮説は無用のものとなった。削除を唱道する者はしばしば所与のテキストを大部分削ってしまう(ヨブ記では、四章、一二章、あるいは一三章のように)。挿入だと申し立てられたものを取り除いてしまうと、「突破口のほうが、残っている城壁よりも、広い」ということになりかねない。
理解できない章句をいじり回すのは最後の最後だというのが正しい学問的方法であろう。本文批評の古い規範、「より難読のものを優先せよ」difficilior lectio praestatは、今も有効である。もともと難しいテキストが善意の写字生によって平易にされるというのはわかるが、明快で、簡単な読み方が難しいものに変えられるということはありそうもないからである。
ロバート・ゴルディス著『神と人間の書(上)』p.71-72より
『神と人間の書』
邦訳書の出版は1977年
原書は1965年に出ています
その時代に
決して 保守的とは言えないゴルディスが
上記のように述べているのは
とても意義深いことです
聖書のどこを読むにしても
「文書資料説」的なアプローチが
主流だった当時において
ゴルディスは
「より難読のものを優先せよ」
という本文批評の規範を
釈義の他の領域にも当てはめて
警鐘を鳴らしています
「理解できない章句をいじり回すのは最後の最後」
この あたりまえの原則が 共有されていれば
破壊的な批評学的方法論にも
歯止めがかかっていたでしょうね
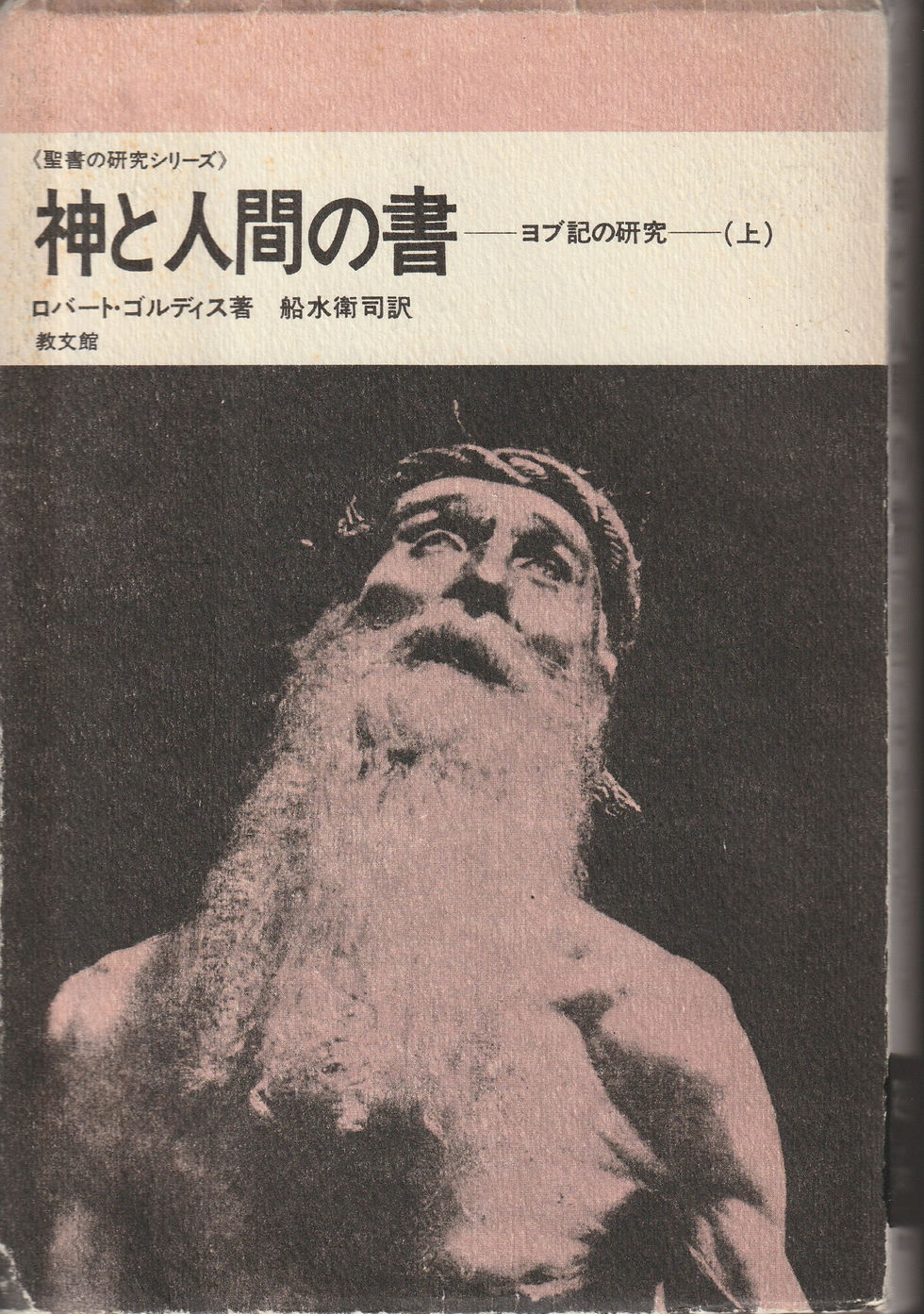


コメント